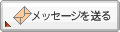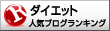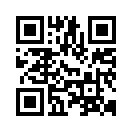2024年10月26日
焼酎と泡盛
焼酎と泡盛
焼酎は酒税法上の定義により、「甲類」と「乙類」の2つに分類され、甲類焼酎と乙類焼酎は、主に以下の3つが異なります。
・蒸留方法(焼酎造りに使用する蒸留器の種類)
・アルコール度数
・原料
甲類焼酎を造るときに使用されるのは「連続式蒸留器」です。一方、乙類焼酎は「単式蒸留器」で蒸留されます。
甲類焼酎のアルコール度数は36度(=36%)未満、乙類焼酎は45度以下です。
泡盛は、日本の税法上では単式蒸留焼酎(かつての乙類焼酎)に分類され、本土の本格焼酎と同じジャンルになります。
しかし、その製法には大きな違いがあるのです。
まず、ほとんどの泡盛が、原料にタイ米を使用すること。
次に黒麹菌を伝統的に使用していること。
さらには、仕込み方法にも違いがあります。
泡盛は、原料の米すべてを米麹にし、水と酵母を加えて発酵させます(全麹仕込み)。
それに対して一般的な焼酎では、まず米麹あるいは麦麹をつくり、それに水と酵母を加えて発酵させ(1次仕込み)、その途中で主原料となる芋や麦、米、そばなどを仕込んでさらに発酵させます(2次仕込み)。
さらに、蒸留段階では、泡盛の多くが常圧蒸留なのに対して、焼酎は減圧蒸留がメイン。
常圧蒸留が原料の個性をより多く出す手法で、減圧蒸留は、口当たりが軽やかで飲みやすく、フルーティーなやさしい香りの酒質になるという特性があります。
もちろん、泡盛にも減圧蒸留、あるいは減圧と常圧のブレンドなど、いろいろな味わいがあり、本土の焼酎にも常圧で蒸留した銘柄もあります。
泡盛に常圧蒸留が多い理由のひとつに、熟成させて風味を高めていく古酒の存在があります。
お酒そのものの個性が強いということが、古酒になったときの味わい深さにも大きく関係するからなのです。


新潟の酒
1. 八海山(はっかいさん): 新潟を代表する銘柄の一つで、淡麗辛口の味わいが特徴です。特に冷やして飲むと、そのすっきりとした味わいが引き立ちます。
2. 越乃寒梅(こしのかんばい): こちらも非常に人気のある銘柄で、芳醇な香りとまろやかな味わいが特徴です。贈り物としても喜ばれる一品です。
3. 久保田(くぼた): さまざまな種類があり、特に「久保田千寿」は飲みやすく、初心者にもおすすめです。上品な味わいが特徴で、食事との相性も抜群です。
4. 新潟県産の純米酒: 新潟には多くの酒蔵があり、各蔵元が独自の純米酒を製造しています。これらはそれぞれ異なる風味を持ち、呑み比べを楽しむのに最適です。
新潟は北東から南西に広い県です。
村上市の宮尾酒造の「〆張鶴(しめはりつる)」
新発田市、菊水酒造「菊水」
五泉市、金鵄盃酒造「越後杜氏」
新潟市には石本酒造「越乃寒梅」がありますし、
他にも宝山酒造「宝山」、福井酒造「峰乃白梅」、高野酒造「越路吹雪」
などなど、記憶から出てくるだけでもまだまだあります。
さらに下って加茂市には「加茂錦」「萬寿鏡(ますかがみ)」
長岡市、恩田酒造「舞鶴」や諸橋酒造「越乃影虎」、河忠酒造「想天坊」
十日町市の松乃井酒造場「松乃井」
南魚沼市、八海醸造の「八海山」はあまりにも有名でしょうし、
湯沢町には白瀧酒造「上善水如(じょうぜんみずのごとし)」も有名です。
上越市、加藤酒造の「清正」も旨い酒ですし、丸山酒造場「雪中梅」も忘れたくないところです。
糸魚川市には加賀の井酒造「加賀の井」がありますし、
佐渡にも尾畑酒造「真野鶴」など、銘酒があります。
餅は餅屋、酒は酒屋。
日本酒の製造所が焼酎をつくる。
時代がどんどん飲みやすいお酒を求めている中、泡盛もその流れに対応しながら
も、一方では古酒にしておいしくなるような製法を、
守り続けているということももう一度考えるべきかも。
焼酎は酒税法上の定義により、「甲類」と「乙類」の2つに分類され、甲類焼酎と乙類焼酎は、主に以下の3つが異なります。
・蒸留方法(焼酎造りに使用する蒸留器の種類)
・アルコール度数
・原料
甲類焼酎を造るときに使用されるのは「連続式蒸留器」です。一方、乙類焼酎は「単式蒸留器」で蒸留されます。
甲類焼酎のアルコール度数は36度(=36%)未満、乙類焼酎は45度以下です。
泡盛は、日本の税法上では単式蒸留焼酎(かつての乙類焼酎)に分類され、本土の本格焼酎と同じジャンルになります。
しかし、その製法には大きな違いがあるのです。
まず、ほとんどの泡盛が、原料にタイ米を使用すること。
次に黒麹菌を伝統的に使用していること。
さらには、仕込み方法にも違いがあります。
泡盛は、原料の米すべてを米麹にし、水と酵母を加えて発酵させます(全麹仕込み)。
それに対して一般的な焼酎では、まず米麹あるいは麦麹をつくり、それに水と酵母を加えて発酵させ(1次仕込み)、その途中で主原料となる芋や麦、米、そばなどを仕込んでさらに発酵させます(2次仕込み)。
さらに、蒸留段階では、泡盛の多くが常圧蒸留なのに対して、焼酎は減圧蒸留がメイン。
常圧蒸留が原料の個性をより多く出す手法で、減圧蒸留は、口当たりが軽やかで飲みやすく、フルーティーなやさしい香りの酒質になるという特性があります。
もちろん、泡盛にも減圧蒸留、あるいは減圧と常圧のブレンドなど、いろいろな味わいがあり、本土の焼酎にも常圧で蒸留した銘柄もあります。
泡盛に常圧蒸留が多い理由のひとつに、熟成させて風味を高めていく古酒の存在があります。
お酒そのものの個性が強いということが、古酒になったときの味わい深さにも大きく関係するからなのです。


新潟の酒
1. 八海山(はっかいさん): 新潟を代表する銘柄の一つで、淡麗辛口の味わいが特徴です。特に冷やして飲むと、そのすっきりとした味わいが引き立ちます。
2. 越乃寒梅(こしのかんばい): こちらも非常に人気のある銘柄で、芳醇な香りとまろやかな味わいが特徴です。贈り物としても喜ばれる一品です。
3. 久保田(くぼた): さまざまな種類があり、特に「久保田千寿」は飲みやすく、初心者にもおすすめです。上品な味わいが特徴で、食事との相性も抜群です。
4. 新潟県産の純米酒: 新潟には多くの酒蔵があり、各蔵元が独自の純米酒を製造しています。これらはそれぞれ異なる風味を持ち、呑み比べを楽しむのに最適です。
新潟は北東から南西に広い県です。
村上市の宮尾酒造の「〆張鶴(しめはりつる)」
新発田市、菊水酒造「菊水」
五泉市、金鵄盃酒造「越後杜氏」
新潟市には石本酒造「越乃寒梅」がありますし、
他にも宝山酒造「宝山」、福井酒造「峰乃白梅」、高野酒造「越路吹雪」
などなど、記憶から出てくるだけでもまだまだあります。
さらに下って加茂市には「加茂錦」「萬寿鏡(ますかがみ)」
長岡市、恩田酒造「舞鶴」や諸橋酒造「越乃影虎」、河忠酒造「想天坊」
十日町市の松乃井酒造場「松乃井」
南魚沼市、八海醸造の「八海山」はあまりにも有名でしょうし、
湯沢町には白瀧酒造「上善水如(じょうぜんみずのごとし)」も有名です。
上越市、加藤酒造の「清正」も旨い酒ですし、丸山酒造場「雪中梅」も忘れたくないところです。
糸魚川市には加賀の井酒造「加賀の井」がありますし、
佐渡にも尾畑酒造「真野鶴」など、銘酒があります。
餅は餅屋、酒は酒屋。
日本酒の製造所が焼酎をつくる。
時代がどんどん飲みやすいお酒を求めている中、泡盛もその流れに対応しながら
も、一方では古酒にしておいしくなるような製法を、
守り続けているということももう一度考えるべきかも。
Posted by sukebo at 07:16│Comments(2)
│呑人・断酒の前に節酒
この記事へのコメント
sukeboさんの姿が見えません。
最後の「かも」でチラッと見えたような・・。
最後の「かも」でチラッと見えたような・・。
Posted by とんび at 2024年10月27日 12:59
パクリながら、学んでます。
おーきに!です。
おーきに!です。
Posted by sukebo at 2024年10月28日 08:21
at 2024年10月28日 08:21
 at 2024年10月28日 08:21
at 2024年10月28日 08:21